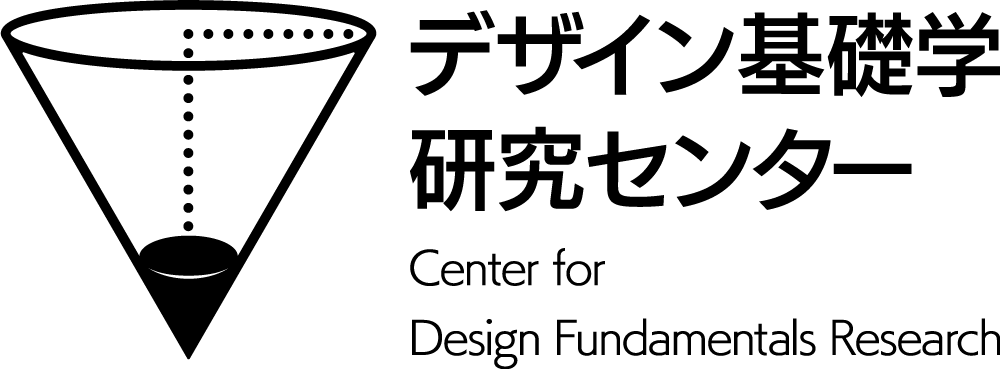ヘパイストス
Hephaestus
古代ギリシャにおいて、ひいては西洋文化全般において職人や工芸の地位は低かった。機械的な技術はつねに人文的な教養に比して第二級のものとされ、それが「専門」であるという理由で近代にいたってもなお、神学・哲学・法学を中心とした大学から排除されてきた。機械的な技術とそれに携わる者たちが知的にも、道徳的にも、かつ美的にも一段と低い存在だと誤って見なされるその例はすでに神話のうちにある。
鍛冶と工芸の神であるヘパイストスは自らの工房で様々な道具をこしらえることを生業とする。ゼウスの妻で結婚の神とされるヘラはゼウスと交わることなくヘパイストスを生むが、ホメロスの『イーリアス』によれば、両足に障害があるという理由で天から海に彼を投げ捨ててしまう。
しかしなにゆえに工芸の神ヘパイストスは血縁においてゼウスから隔てられ、さらに生まれながらの障害を持つ身として神話に描かれなければならなかったか。考えてみるにそれは工芸が生命の必要に拘束されていたためであったといえる。生命の必要を満たすことは、死すべき存在としての人間にふさわしく、生命から自由であるはずの神々にはふさわしくない。その点でヘパイストスの製作物のうちには不純なもの、つまり実用性が混入しており、したがってそれは神の属性たる善美の障害となるのである。いうまでもなくこのような障害観は今日では到底受け入れられるものではない。
とはいえ神々といえども武具や道具は必要である。ヘパイストスはゼウスから様々な用事を言いつかり、彼のためにまるで様々な実用道具を拵える使用人のように扱われる。それゆえヘパイストスはオリュンポスの神々の一員であるとしても、つねに第二級のもの、歪んだものとして表象される。
神話が説くところによれば、工芸という歪みはヘパイストス自身の容姿や性格にも及んでいる。オリュンポスの神々の多くが容姿端麗とされるのに対し、彼はそうではない。しかもそうした自分の姿に劣等感を持ち、恨み深く、それゆえにこそ美に強烈な憧れを抱く存在として古代の文献に彼は描かれるのである。
ギリシャ神話はローマの著作家の手によってラテン語に翻訳され、ローマ神話の中に組み込まれていく。紀元前64年ごろに生まれたラテン語の著作家ヒュギーヌスは、ヘパイストスがかつて自分を虐待した実母ヘラを、美的に粉飾された機械、すなわち宝石をちりばめた黄金の仕掛け椅子に誘い込み、拘束する話を伝える。
プラトンによればひとが美の有機性に憧れてそれに魅惑されるのは、現状の生活を営むための必要、つまり生命の機械性から解き放たれるためである。だがその椅子の本質は機械仕掛けの拘束具である。ここにはのちに19世紀において応用芸術と呼ばれるデザインの類型と同様のものが見出される。イギリスのヴィクトリア朝期の消費者たちが、製品を装飾する応用美術の絢爛さに魅惑され、結局は資本主義と帝国主義の手中に陥っていくように、古代ギリシャの物語においても神々は美に誘われ、欺かれて、必然性の手に落ちるのである。
ヘパイストスはヘラを解放する条件として、美の神アフロディテとの結婚をゼウスに要求する。ゼウスはこの要求に応じ、ヘパイストスはアフロディテと結婚生活を始める。しかしそれは長くは続かない。周知のように、美の化身アフロディテは容姿端麗とは言い難い夫との婚姻生活に飽き足らず、夫の留守中に戦争の神アレスを夫婦の寝台に引き入れて恋仲となる。ホメロスの『オデュッセイア』は、楽人デモドコスがオデュッセウスに次のように歌った様子を伝えている。
ヘパイストスは、ひどく胸が潰れるこの話を耳にして、恐るべき企みを胸中に抱きつつ、ひとり鍜治場へと歩み入り、床の上に巨大な金床据え付けて、恋人たちがその場で身動きできぬよう、断ち切るも抜け出すもかなわぬ鎖を鍛造した。鎖の網は蜘蛛の糸のごとくにか細く、祝福された神ですら誰も見分けができぬほど、念入り細工の極みにあったのだ。(Odyssey, 8-270)
ヘパイストスとの生活が示唆しているのは利便、安全、体制、そして単調な反復である。これに対して戦争の神アレスがアフロディテに提示するのは美貌と官能、ならびに背徳のスリルである。ホメロスは美の神を、安全と退屈ではなく危険とスリルの方に赴く存在として描き出す。密通を知ったヘパイストスは、美と破壊が融合する頂点、生の自由の極点を機械の手で捕捉し、神々の眼前に晒し、そのうえで決定的な言葉を吐く。
二人の閨の熱がすぐ冷めるとて、
この恥知らずの女の代わりに父が手に入れた、
婚姻の贈物をそっくりそのまま返すまで、
網と鎖が二人をしっかと掴まえ離さない、
その娘は美しくはあるが、自分を抑え得なかったのだから。 (Odyssey, 8-317)
美が内から己れを自然に形象化できないなら、機械が外から型に嵌めるしかないとヘパイストスは考える。婚姻とはまさにそのような拘束であり、その拘束をもたらしたのは、娘の所有者である父親との取引、すなわち美と実用物との交換である。このようにヘパイストスは有機性と機械性を引き換えにし、そうすることで両者を混ぜ合わせてしまう。
アポロドーロスによれば、ヘラは男と交わることなくヘパイストスを生んだとされる。その理由として、ゼウスがヘラと交わることなく自分の頭部からアテナを直接誕生させたのをヘラが見たためと伝える説もある。これに従うなら、競争と卓越の神アテナはまさに全能の神ゼウスの頭脳を引き継ぐ存在であり、それと対照をなすのがヘパイストスということになる。そしてアポロドーロスが伝えるところによれば、アフロディテに去られたヘパイストスは、その傷を癒すため眼前のアテナに欲情する。
アテナは武器を調えるためヘパイストスを訪れた。だがアフロディテに去られたヘパイストスは、アテナに欲望を抱いて彼女を押し倒そうとした。アテナは逃げようとした。彼は何としてでも彼女に縋りつき(というのも彼の足には障害があったから)、彼女と交わろうとした。アテナは身持ちが固くしかも処女であったので彼に応じなかった。それで彼は彼女の脚に子種を播いた。アテナは嫌悪して毛でこれをふき取り、地に投げた。(Apollodorus, 3-14-6)
アテナはヘパイストスの工房を自分の装備品のために訪れる。ヘパイストスはこれに対してアテナに美を見出し追跡する。アテナが交わりを知らない純粋性を保つのに対して、ヘパイストスは業務とエロスを混ぜ合わせる。襲い掛かる生物の欲求から卓越の神アテナは必死に逃れようとする。だが逃げ切れぬその脚は機械男の下半身に汚されてしまう。オリュンポスの神々の最高位に位置するのは、アフロディテやアテナのみならず、月と狩りの神アルテミス、文芸と音楽の神アポロンといった、生活から無縁で純粋な神々である。こうした第一級の神々の高さに比して、ヘパイストスがかくも惨めに低く描かれていることのうちには、労働への、工房と職工に対するギリシャの侮蔑が表現されている。自由であるべき有機性のうちへと、自由を拘束する機械性を混ぜてくることへの西洋文化に独特の嫌悪がそこに表出している。
古代の神話とそれを語る詩人の筆には、家父長的支配の影が色濃く差しており、女性を贈与物で獲得する習慣や婚姻制度に則った女性の評価など、今日では受け入れがたい当時の価値観が反映している。そうした当時の価値観に則って職人と工作が同時に低く位置づけられている。今日のデザインは、西洋文化の価値観に立脚しながらも、工芸への侮蔑的な価値評価をいかに克服し、「つくること」をいかに高貴に定義するかに心を砕いてきたといえる。
参考文献
アポロードス『ギリシア神話』(高津春繁訳、岩波文庫、1978年)
ホメロス『イーリアス』(松平千秋訳、岩波文庫)18歌。
ヒュギーヌス『ギリシャ神話集』(松田治・青山照男訳、講談社学術文庫、2005年)、第166話 エリクトニオスの項目を参照。
ホメロス『オデュッセイア』(松平千秋訳、岩波文庫、1994年)
吉田敦彦『ギリシア・ローマの神話 人間に似た神様たち』(ちくま文庫、1996年)、72頁。ただしアポロードスは、「一説によれば」との限定付きで、ヘパイストスがゼウスの頭を斧で打ってアテナを誕生させたという説を紹介している。