第32回デザイン基礎学セミナー『システムと抵抗:デザインの限界点をめぐって』
デザインは合理的に機能し、スケーラブルで代替可能な「システム」として物事を扱う視点を持つ。だが、例えば水俣における社会運動はシステム化されたデザインに対する「ひと」としての抵抗でもある。本来、デザインは代替的な現実を創り出すとともに、その創出者の変容をも結果する。デザインが関与してきた社会の歪みをデザインの力で乗り越えることは可能か。
講師
水内智英 Tomohide MIZUUCHI(京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構 准教授)
デザイン研究者・プロジェクトディレクター/京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構准教授。
デザインの在り方それ自体を問いなおすための研究に取り組み、とりわけソーシャルイノベーションやシステミックデザイン、幅広い主体との協働デザインに関する研究活動、実践的プロジェクトを行う。著書に『多元世界へ向けたデザイン』(2024、共監訳)、『ヴィジュアルリテラシースタディーズ』(2018、共著)など。
日時
2025年1月30日(木)18:00~20:00(開場 17:45~)
会場
九州大学大橋キャンパス・印刷実験棟2F+オンライン開催
*ご関心のある方はどなたでも自由に参加できます。参加ご希望の方は前日までに、こちらの申込みフォームからお申込みください(締切:1/29、講演は日本語のみ The lecture will be given in Japanese only.)。
*オンライン参加をご希望の方は、上記フォームに入力頂いたアドレスに当日、URL等のご案内をお送りします。事前にZoomの最新版をダウンロードしてください。
主催
九州大学大学院芸術工学研究院・デザイン基礎学研究センター
共催|九州大学芸術工学部未来構想デザインコース
問い合わせ先|古賀徹
designfundamentalseminar#gmail.com(#は@に置き換えてください。)
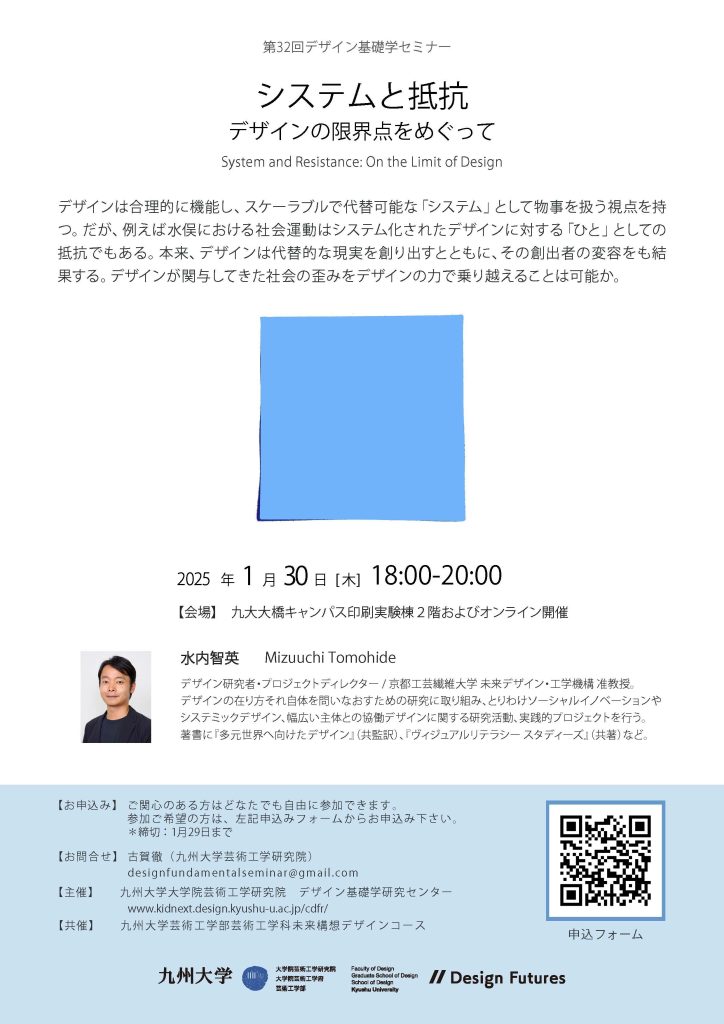
レビュー
厄介な問題とシステミックデザイン
「厄介な問題」とは、原因と結果という直線的図式に基づく予測や制御が困難な状況を指す。水内さんが挙げた例では、Co2排出削減のためにイギリス中の自動車を電動化しようとしても、世界の年間総生産量のおよそ2倍の量のコバルトが必要なため、台数も同時に減らす必要がある。しかもコバルト生産の多くが零細鉱山での劣悪な労働によっている。
ここで無理に電動化を進めると、価格の高騰や労働条件のさらなる劣悪化を招き、結局のところ電動化は進まない。こうした「意図せぬ効果」を招かないためには、数多くの要素間に複雑なフィードバック・ループが存在することを認識し、その「システム」全体を理解し可視化する必要がある。これがシステミックデザインの基本的な考え方である。
システミックデザインにおいては、単純な因果論的アプローチの代わりに、複雑なフィードバック・ループが織りなす相関図が重要な役割を果たす。複数のループ交差点のうちからレバレッジ・ポイントと呼ばれる特に重要な地点を特定し、そこへの手当てを行うのがアプローチ方法となる。
こうした水内さんの解説を聞きながら連想したのは、西洋医学と東洋医学の対比であった。西洋医学、とりわけ感染症治療においては、病原体を発見してそれを抗生物質で叩くという単純な因果論的アプローチが主流を占めている。これに対して東洋医学の鍼灸療法においては、まずは全身の状態を問題にし、神経系統の特定のツボを刺激するという方法が採られる。システミックデザインとは、西洋技術の先端において姿を現すいわば東洋的アプローチといえる。
とはいえ、因果関係による因果関係からループの相関図へと認識の図式やアプローチを転換したとしても、依然としてその「システム」の外部が存在し、その外部はデザイナーの認識を超えているという点は変わりない。そうである以上は、システミックデザインもまた「厄介な問題」がもたらす「意図せぬ効果」から逃れられないという疑いが生じるであろう。因果関係モデルも、システムアプローチも、問題をコントロールしようとする点では同じである。
これに対して水内さんは、システミックデザインに内在する「コントロール幻想」を批判し、「システム思考ではなく、システム実行」(Design Council and The Point People, 2021, System-shifting Design, p. 25.)というダン・ヒルの言葉を引用する。これはつまり、かの相関図はシステム全体の状況を最終的に可視化するものではなく、あくまで介入を行うための手引きのようなものであり、デザインの実践とともに修正される暫定的なものにすぎないということなのだろう。だがそうだとすれば、もはやデザイナーはシステムを全面的に可視化することはできず、むしろシステムのうちに取り込まれることになる。このときシステム全体を理解したうえで初めて介入が可能になるという、システミックデザインの当初のテーゼは維持できなくなろう。
システミックデザインの可能性を探っていた水内さんは、水俣に出会い、自らのシステミックな方法論に動揺を感じたという。とりわけ水俣病の患者である緒方正人さんの思想と実践に強い衝撃を受けたと水内さんは言う。緒方さんは認定申請を自ら取り下げ、被害と認定と補償からなるいわば公害補償システムを拒絶した。彼は自ら編んだ「常世の舟」に乗り込み、櫓を漕いで、毎日のようにチッソ水俣工場へと赴き、その正門前にテントを張り、通勤するチッソの人たちとただ話をするという行動を始めた。それは、被害者と加害者という既存の役割図式を超えて、自己の「存在」をあえて曝すことで、役割に埋もれるチッソの人々からその「ひと」としてのあり方を引き出し、「ひと」と「ひと」との関係性を回復するものであった。
システミックデザインがフィードバック・ループを複数化して全体をとらえようとするのに対し、水俣の実践はそうした認識・介入スキームの一切をあえて拒絶し、人間存在の全体、ひいては水俣病事件総体の本質に直接迫ろうとする。システミックがデザインシステムの相関図をアプローチの手段にするのに対し、緒方さんは「常世の舟」をそこへと到る乗り物にする。そのように考えるならば、一見対立するどちらの方法も、自己と他者、そして結局のところ社会全体を、その行き先が不明なままにとにかく変容させることを意図するデザインなのだということができる。どちらの実践も、硬化した既存のシステムを超えて、変化の余地を生み出し、その変化がよい方向に向かうことを何かしら信じているのである。 (古賀徹)
