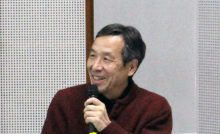第5回デザイン基礎学セミナー『社会を形づくること:デザインが社会的なプロセスになること』
デザインの対象が「社会」に広がっている。ビジュアルやプロダクト、建築や環境など人工物に形を与えてきたデザインが、新たに人びとの結びつきやそこから生まれる営みを形づくることにその射程を広げている。そのことと重なるように、わが国のあちらこちらで「自分たちが暮らしたい社会を自分たちでつくろうとする活動」が生まれている。そこにはじまっている、デザインの専門家ではなく市民が主体となる社会づくりのデザインについて考えてみる。
講師
須永 剛司 Takeshi Sunaga(東京藝術大学美術学部デザイン科教授)
多摩美術大学立体デザイン科を卒業しGKインダストリアルデザイン研究所勤務。デザインの現場を離れて筑波大学大学院で認知科学とデザインの学際領域を学び、87 年筑波大学術博士。イリノイ工科大学、多摩美術大学、スタンフォード大学での研究を経て、98 年多摩美術大学に美術学部情報デザイン学科開設。2015 年より東京藝術大学美術学部デザイン科教授。
日時
2019年1月25日(金)16:30-18:30
会場
九州大学大橋キャンパス 音響特殊棟1F 録音スタジオ
レビュー
「実存は本質に先立つ」というのは、サルトルの有名な言葉である。人間の生は一切の説明に先立ってすでにそこに存在するのであり、その本質を規定する言説はすべて後付けである、というのがその主旨である。これを須永さんは、「つくることのプロセスはつくらないと存在しない」と表現する。状況うちに身を投げ出し、わけもわからず何かを作り出してしまう。そしてその後にはじめて、どのような意図とプロセスでそれをつくったかを自分なりに表現するのである。
デザインがそれ以外の「つくること」から区別されるのは、この表現、つまり自らの制作物の「本質」をあとから合理的に説明できるかにかかっている、と須永さんは言う。デザインの条件をこのように捉えることによって、デザインは専門家の職能から、生活者の能力へと拡張される。つまりその能力は、「なぜそれをやっているかがわかること」なのだ。デザインの専門家とは、生活者が持っているその能力を引き出し、生活者とともに考える技術者なのである。
その意味でデザイナーとはタフな素人である。医療者と患者との関係は非対称である。そこにはミクロな権力が働いている。両者はわれ知らず、そうした関係性を「つくって」いる。デザイナーの役割は、「そこでつくられていること」を可視化し、なぜそのような関係がつくられているのかをわかりやすく表現し、その両者の関係をよりよいものに変えるにはどうしたらよいかを考えるよう、人々にうながすことにある。それはアクションを提起することであり、その意味でデザイナーとはアクティヴィストなのだ。
事前に計画し、それを実現するというのが近代デザインの基本である。それはまずもって本質を規定し、そののちにその存在を生産する。そこでは本質に外れた存在の要素は否定される。このかぎり計画は人間の生を箍に嵌める。
これに対して須永さんのデザイン実存主義は、いまここにある人間の生、その存在をまずもって肯定する。生の〈いま〉に歓び、人々の自己肯定感をさらに強化することが、デザインが生みだす価値なのだ。「社会とはまずもってそこにあり、それを善くすることがデザインである」という彼の言葉は、そうしたことを意味しているのである。
(古賀徹)