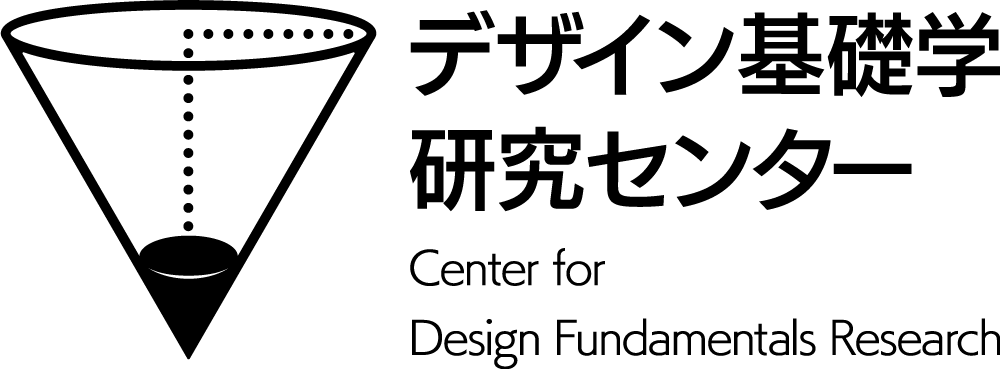第9回デザイン基礎学セミナー『密室を解放するデザイン──境界を超える社会・空間・生活・思想を求めて』
近代以降、特に20世紀以降はある意味生活空間、社会空間の密室化が進んだ時代であった。個人の権利が守られ、境界が設けられ、人々はコンクリートといった近代の建材によって区切られた空間に生まれ育ち、生活をするようになった。それは同時に社会構造や思想、地域デザイン、家屋のデザインにも表現されている。ここではそれを「密室化」と呼ぶ。「密室化」は学問的アプローチにも見られ、全人格的知恵や思想よりもより専門化し、区切られた思考が重んじられるようになった。家庭も、学校も、それぞれ空間的にも社会的にも密室化し、そこに新たな暴力や閉そく性が生み出されている。21世紀はこの20世紀の閉そくを脱するために、「密室の開放」を求める時代であるべきだと考えている。開かれた空間、開かれた社会、偶発的な出会いやコミュニケーションによって即興的に構成される世界。これが生命系をより豊かにし、自らの閉そく性を打破するために人類が獲得すべき方向性なのではないか。それを筆者が長年のフィールドとして通ってきた中国内陸部の黄土高原の村を一つのモデルに描いてみたい。
講師
深尾 葉子(大阪大学大学院言語文化研究科・言語社会専攻教授)
1985年大阪外国語大学国語学部中国語専攻卒業。1987年大阪市立大学東洋史専攻前期博士課程修了。同年大阪外国語大学助手、講師、助教授を経て、2007年大阪大学との統合により経済学研究科グローバルマネジメントコース准教授に。2018年大阪大学言語文化研究科、言語社会専攻に戻り2019年より同研究科教授。その間、中国内陸部黄土高原と日本を往復し、一つの村を拠点に25年以上にわたる断続的な参与調査を行う。
著書に『魂の脱植民地化とは何か』(青灯社)『黄砂の越境マネジメント──黄土・植林・援助を問いなおす』(大阪大学出版会)『日本の男を喰い尽くすタガメ女の正体』『日本の社会を埋め尽くすカエル男の末路』(講談社α新書)。共著に『黄土高原の村──音・空間・社会』(古今書院)、共編著に『黄土高原・緑を紡ぎ出す人々──「緑聖」朱序弼をめぐる動きと語り』(風響社)『満洲の成立──森林の消尽と近代空間の形成』(名古屋大学出版会)、『香港バリケード』(明石書店)などがある。
日時
2019年7月12日(金)16:30-18:30
会場
九州大学大橋キャンパス デザインコモン1F

レビュー
物事を明らかにし、問題を見定め、それを効果的に解決するためには、やはりなんといっても視点と枠組みが必要である。フレームなしにデザインも学問も成立しない。だが、科学化し精密化するほどにデザインは、自ら定めた方法に従い、外部から遮断された密室を形成し、そのなかの虜となる。そのとき、その方法枠組みから排除した要素が決定的な作用を果たしてしまい、デザインは失敗する。こうした逆説は、デザイン学では「邪悪な問題 wicked problem」と呼ばれている。
黄土高原の住居や村落は、川の支流の分岐に沿って発達していると深尾葉子さんは言う。そこには、個人の視点と枠組みが、家族や集落、そして流域全体へと次々に脱フレーム化され、普遍性へと開かれていく情報構造がある。その脱フレーム化は、あらゆる階層で展開される人々の「充実した語り」によって実現されるという。
充実した、いやむしろ、充溢した語りとは何か。それは目的を定めず、情報の強度によってのみ語り尽くされる「おしゃべり」である。会議や学術論文の言語が、視点とフレームを定めて語られるのに対し、おしゃべりはいつも、それを相対化し崩壊させ、目的の達成を困難にする。
だが、脱フレーム化された言語は、その創造性や自己革新の根を一見無秩序な語りの充実のうちにもっているのだ。深尾さんは、語りが脱フレーム化され、無目的に充実されゆくその論理それ自体に則って、デザインがなされるべきだと主張する。そんなことが可能なのだろうか。
事実、黄土高原において、フレームと手順と予算を事前に設計して、計画的に実行された植林事業は悉く失敗した。だが、フレームを超える人々の語りに根ざしたやり方だけが、その中心人物がいなくなった後でも人々によって自発的に継承され、林や森を持続的に創りだしていると深尾さんはいう。
生命を維持するためのフレーム化が状況を切り縮め、結果として生命を圧迫するとすれば、その「邪悪さ」に対抗するデザインは、つねにおしゃべりの自発性とともにあるだろう。そうしたデザインだけが、生き生きとした生命をつなぐことができると思われる。
(古賀徹)