第16回デザイン基礎学セミナー『Post-Speculative Biologies』
21世紀に入り、バイオテクノロジーは数々の革新を見てきた。iPS細胞、DNAシークエンスの低コスト化、CRISPR、そして分析から合成へと向かう生物学の根本的な移行である。こうした「読みとり専用」から「書き込み可能」への変化は、新しいメディアの出現を示唆してもいる。アーティストとデザイナーの役割と責務とは、文化にとってのワクチンとして機能しうるような望ましい未来とさほど望ましくはない未来を想像し、創り出すことである。Common Flowers三部作やBLP-2000、the Copyrightシリーズ、そして、The Point Mutators – Legally Greenなど、進行中ないしは今後のプロジェクトを紹介しつつ議論してみたい。
講師
ゲオアグ・トレメル(バイオ・アーティスト)
1977年オーストリア生、東京を活動拠点とするアーティスト。ウィーン応用美術大学でメディアアート、RCAでインタラクションデザインの修士号を取得。2005年に福原志保とともにアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「BCL」をロンドンで結成。代表作として、Biopresence、the Common Flowers Series、Ghost in the Cellなどを発表。現在、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターDNA情報解析分野研究員、早稲田大学理工学術院・岩崎秀雄研究室主宰の生命美学プラットフォーム「metaPhorest」客員研究員、また、バイオテクノロジーの可能性について実践・議論するプラットフォーム「BioClub」プログラムディレクターを務める。
日時
2020年11月20日(金)16:30-18:30 開場16:00 開演16:30
会場
オンライン
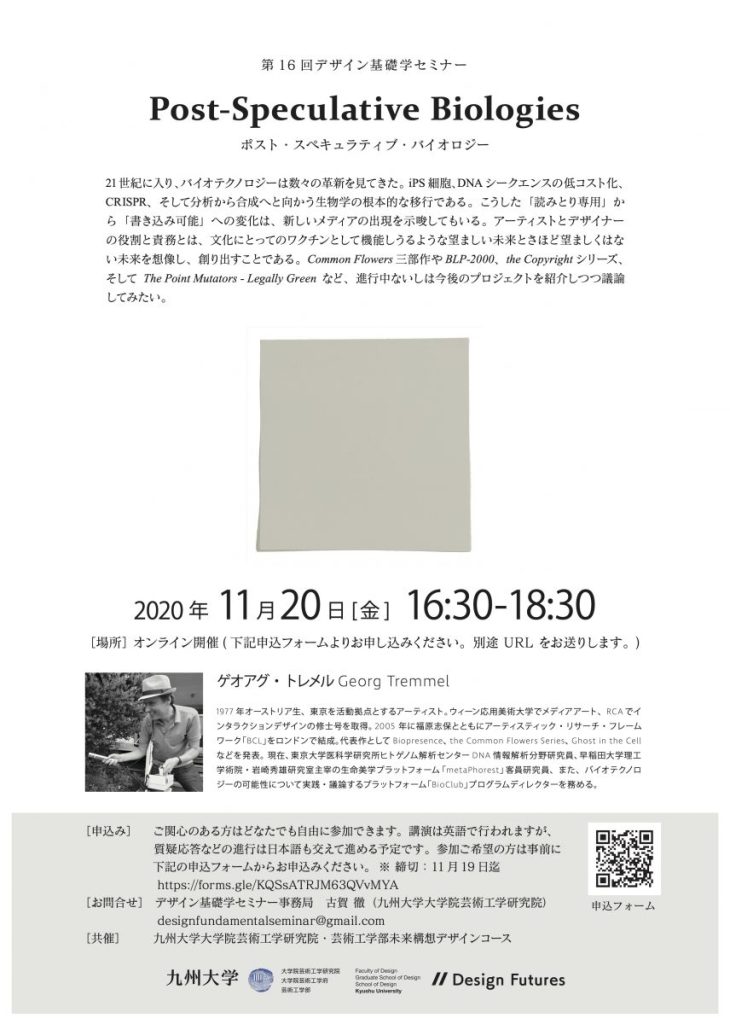
レビュー
まずは「ポスト・スベキュラティヴ・バイオロジー」というタイトルについて、それぞれに聞き覚えのある言葉ではあるものの、その組み合わせが引き起こす違和感から始めてみたい。〈スペキュラティヴ〉という形容詞は昨今、デザインと接続されることで、未来志向の「思弁的」ないし「投機的な」実践として注目を集めている。ただし今回、この言葉に続くのはデザインでも哲学でもなく、実験室での厳密な手続きによって生命活動の解明を試みる学問の〈バイオロジー〉である。また、この疑問に輪をかけるかのように、「以後」を意味する〈ポスト〉という言葉が全体に冠されてもいる。スペキュラティヴなかたちをとる生物学の後に、いかなる未来が開かれているのか。トレメルさんの講演ははたして、これらの疑問に実に興味深いかたちで応じるものであった。
スペキュラティヴ・デザインとは概して、ユーザーである人間にとっての意味や目的を中心化してきたデザインの実践に批判的なスタンスをとり、持続可能な未来を志向しつつ必ずしも有用性のみに還元されない問題提起型の実践を指す。近年、この動向の震源地となった英国RCAからアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーの発表した仕事は、日本でも翻訳書などをつうじて広く知られている(『スペキュラティヴ・デザイン』BNN、2016[2013])。そのなかに掲載された挿絵は、現在から放射状に発せられたタイムライン上に四つの「P」から始まる未来のかたちを指し示している。すなわち、「起こりうる(Possible)」、「起こってもおかしくない(Plausible)」、「起こりそうな(Probable)」、そして「望ましい(Preferable)」未来のことである。著者たちはこの最後の「望ましい未来」を探究すべく、次のように問いかける。「デザインは人々が消費者市民としてより積極的に未来づくりに参加するのを手助けできないだろうか?できるとすれば、どうやって?」(同書、30頁)。
ちょうど同時期にRCAでインタラクションデザインを学んだ経歴を持つトレメルさんは、この未来予測図の下敷きになった典拠として、政治学者のC・ベゾルドとT・ハンコックが1994年にWHOの機関紙に提出した「未来の類型図」を確認してみせる。それによって明らかとなるのは、先の図式から消し去られてしまった項目があるという事実である。具体的には、四つの未来のうちに斑点状に散在する点であり、それぞれに「ワイルドカード」と名指されてもいる。「何が起こるかわからない」または「なんでもあり」を意味するワイルドカードを提出すること、それこそがアーティストの役割ではないか、トレメルさんはこう問いかける。
福原志保さんとのアーティスト・ユニットであるBCL名義のものを含め、これまでにトレメルさんが発表してきた作品は実際、こうした狙いを如実に具現するものであった。たとえば、日本の飲料メーカーであるサントリーが発売した商品に、遺伝子組換え技術を用いた青いカーネーションがある。こうした生命の操作可能性が何の議論もなしに販売され、純粋に観賞用の商品として応用されていることに驚きを覚えた二人は、自室に用意したDIYバイオラボで、その遺伝子組換えのプロセスを生物学的に解明しようとする。彼らの代表作《Common Flowers/Flowers Common》は、ときに「ワンカップ大関」の空瓶を使って園芸家のようにカーネションの切り花を育て、それでいて組換えられた遺伝子を逆向きに解体して仕組みを解明するリバース・エンジニアリングのような手続きをとる。こうして「特別な」花を「普通の」花に変換しようとする彼らの試みは、自然の所有をめぐる問いを投げかけることになるだろう。
また、こうしたDIYバイオロジーやバイオハッキングの展開がそれと知らぬ間に生物兵器の開発に与するなどのリスクを帯びていることにも、トレメルさんは意識的である(FBIは実際、バイオハッカーを招聘した会議を開催して、その手の内を把握しようとさえしている)。実の弟との共同作品であるという《Resist/Refuse》は、毒性を持つバクテリアに感染したネズミを入れた日本軍の生物兵器に着想を得て、そのための容器を金継ぎで再構成した造形作品である。一方で《©️HeLa: Copyright in Images》は、1950年代に黒人女性の癌細胞から分離され、彼女や遺族にも無断のまま現在も実験用の細胞として利用され続けているHeLa細胞が、培養されることで「おのずと」シャッターを切るという実験的な作品である(この作品を東京で展示するはずの初日が、コロナ禍によるギャラリーの閉鎖と重なってしまったことは、ただの偶然とは片付けられない皮肉にも思われる)。



これ以外にも数々の実践が紹介されたのだが、それらに共通するのはDNAや細胞のような生物学の素材を「読み取り専用」から「書き込み可能」なものへと変容した──これも記憶に新しい遺伝子技術のCRISPRが実現したように──新しい表現メディアとして理解する態度であるだろう。この古くて新しいメディアが、単なる物質的な支持体ではなく、私たちを取り巻く環境milieuを指していること、そして、そのことを踏まえた作品の意義を「文化にとってワクチンとして作用するようなジレンマや混乱を創り出す」ことだと指摘することによって、講演は締め括られた。
もちろん会場からの質疑でも議論が交わされたように、文化のうちでワクチン接種によって予防すべき病や感染とはいったい何か、という問いは開かれたままである。それはまたコロナウィルスに限らず、情報技術によるフェイクニュースなどの「感染」にも事欠かない現在に喫緊の問題であり、そして、それらを病とみなす根拠や権利が何に求められるのかという倫理を問い直すことにもつながる。この問いに応えるためにも「ポスト・スペキュラティヴ・バイオロジー」という名のもとに、単に明るい未来を見通すと同時に「暗い」過去を冷徹に見直すことがますます重要な手続きとなるだろう。
(増田展大)

