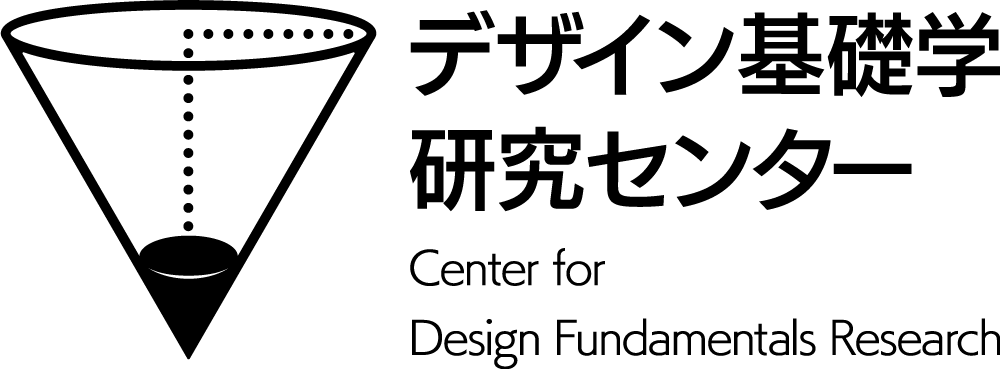第29回デザイン基礎学セミナー『文化的アイデンティティとしての科学技術〜東アジアの事例から』
科学技術が、ある国や社会の文化的アイデンティティを強化することがある。かつての日本の家電製品やアメリカの宇宙開発などが好例で、科学技術は成果が分かりやすくインパクトが大きいが、それゆえに愛国主義を助長するなどの負の側面もある。台湾を事例として、文化的アイコンとしての科学技術のあるべき姿やデザインが果たす役割などを検討する。
講師
佐倉統 Osamu SAKURA(東京大学、理化学研究所)
1960年東京生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。ブリティッシュコロンビア大学客員研究員、三菱化成生命科学研究所、横浜国立大学経営学部、フライブルク大学情報社会研究所を経て、現在、東京大学大学院情報学環教授、理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー。専攻は進化生物学だが、最近は科学技術と社会の関係についての研究考察がおもな領域。長い長い人類進化の観点から人間の科学技術を定位するのが根本の興味である。
日時
2024年2月14日(水)17:00~19:00(開場 16:45~)
会場
九州大学大橋キャンパス・芸術工学図書館1階閲覧ホール+オンライン開催
*ご関心のある方はどなたでも自由に参加できます。参加ご希望の方は前日までに、こちらの申込みフォームからお申込みください(締切:2/13、講演は日本語のみ The lecture will be given in Japanese only.)。
*オンライン参加をご希望の方は、上記フォームに入力頂いたアドレスに当日、URL等のご案内をお送りします。事前にZoomの最新版をダウンロードしてください。
主催
九州大学大学院芸術工学研究院・デザイン基礎学研究センター
共催|九州大学芸術工学部未来構想デザインコース

レビュー
台湾において「国」としてのアイデンティティは実に複雑である。親日としてのイメージを見聞きすることが多く、最近では中国との政治的な緊張関係が頻繁に報じられている。日本と同じように、島嶼としての特徴から物理的にイメージこそしやすいが、少なくとも私は恥ずかしながら、その歴史を十分に知らずにいた(今も、ではあるが)。
この土地にも当然ながら先住民にあたる人々がいて(台湾では「原住民」と表記する)、17世紀にオランダに統治された後、大陸側の清朝に抵抗する明朝の拠点となるが、まもなく1683年に大清帝国に領有された。日清戦争後の1895年から大日本帝国による統治が続き、大戦後は蒋介石に始まる中華民国の時代に入るが、ここでもさまざまな混乱を経験しつつ、最近では東南アジアを中心に多くの移民を受け入れているという。
かくも民族や言語が混交してきた台湾の歴史を、浅学を承知でごく簡単に振り返ってみたのは、佐倉さんの研究されている科学技術と社会の関係が、そうした「国」の成り立ちや歴史と深く関連するからである。科学と技術にはそれぞれ異なる歴史的な起源と変遷があるものの、とりわけ近代以降に両者は「進歩」という旗印のもと、密接に重なり合いつつ展開してきた。と同時に、特定の科学的な知見をもとに発明された技術について、それが世に出る以前に想定されていた意図や狙いがそのまま社会に通用することは少なく、むしろ各々の時代や地域の生活や利用者と密接に連動して独自の価値や機能が形成されていくことになる──その具体的なプロセスを明らかにするのが、佐倉さんの専門とする科学技術社会論である。
このことをわかりやすく示す事例として、近代以降の科学技術はしばしば、それを主力産業とする国を象徴するものとして語られてきた。たとえばアメリカ合衆国は冷戦下、その国力を宇宙開発や自動車・航空機産業というかたちで誇示してきたのであり、そうした「開拓」精神が現在のIT産業へと受け継がれているとの指摘もある。ヨーロッパであれば、他の国と比べて厳密かつ堅牢なドイツの自動車がその国民性と結び付けられるだろう。アジアでも、日本であれば家電製品から自動車、最近のアニメ産業が、または韓国であれば情報通信技術(独自のアプリ)などがそれぞれ代表的な事例となる。このいずれの事例にも、意匠であれ設計であれ、独自の「デザイン」がともなうことは言うまでもない。
こうした理解を前提として東アジアでフィールドワークを進めた佐倉さんは、昨年2023年9月からの台湾での在外研究中に壁にぶつかってしまったのだと率直に打ち明ける。AIやロボットがいかに文化的に意味づけられているかを検証しようとした経緯について、詳しくはこちらで執筆された記事に詳しいが、一節を引用するなら、台湾では「時間軸と地域差が絡み合った網の目のような民族と文化の多元性が、濁流のように社会の底を流れ、あちこちで渦を巻いている」のだという。どういうことだろうか。
あらためて日本を事例にすると、講演では梅棹忠夫による文明論的な視座を引いて述べられたように、科学技術の進展に対する独自の感受性が指摘されることが少なくなかった。それを「(テクノ)アニミズム」と呼ぶことには一定の反論もあるが、たとえば、最先端の犬型ロボットを生産する一方で、故障して動かなくなったペットとしてのそれを「供養」するところには、なるほど独自の科学技術観が浮かび上がるようにも思われる。ところが、台湾で同様の話題についてインタビューをしてみても、当のロボットやITからどんどん話が逸れていくばかりか、科学技術の「台湾らしさ」について深化させるにはいたらなかったのだという。その理由のひとつは、冒頭で触れた台湾の歴史的背景に由来する国家/民族としての多様性にあるのだろうと、佐倉さんは指摘する。先に見たような歴史的な経緯から、台湾では統治する国が変わるたびに言語が変わることもあれば、中国語のうちでも話者の多い言語が支配的になりつつも他のものと複雑に混交していく。結果として、その国を象徴する文化的なステレオタイプが、良くも悪くも、台湾には成立しにくいことがわかったのだという。
ただし、テクノロジーに焦点を絞って言えば、台湾でのフィールドワークでは「半導体」という返答が少なくなかったそうだ。なるほど、世界的な半導体メーカーによる大規模工場の建設が熊本で進められていることもあり、そうしたイメージが定着するような未来もそう遠くはないのかもしれない。ただし、先の事例とは異なり「半導体」という素材(部品)が国を代表する技術になる、とはいったいどういうことなのか。佐倉さんはこの問いについて、製品(全体)が文化的な象徴となった上記の国々との関係を独自にマッピングすることで講演を締めくくった。
その後の議論では、日台間で貿易関係の仕事にあたる参加者から、台湾゠半導体というイメージもIT産業に従事する一部の人間に限られたものであって、必ずしも国民全体に広がってはいないとの指摘も提出された。きっと実情はそうなのだろう。だが、そのことを踏まえても「半導体」という技術が提出されたことが、私にはとても示唆的に思えた。最後に、そのことに触れておきたい。
まず半導体と言われても、それはほとんどの場合に不可視である──佐倉さんによる先の問いも、このことに端を発しているのだと思う。トランジスタや集積回路であればまだしも、その素材として利用される半導体を直接目にすることはなく、その性質(導電性)についての物理学的な原理にまで理解はおよばない。一方で、その半導体なしにはありえない集積回路によって身の回りの電子機器や情報機器が稼働していること、むしろ自動車や産業機械、家電にPCやスマホまで、日常生活がそれに依存した状態にあることを、私たちは知識としては理解している。航空機や自動車、ロボットのような外見上の派手さはなくとも、半導体産業が好景気をたどるのは、それに依拠した装置群が目に見えないまま私たちの身の回りに増殖しているからであるにちがいない。私たちはそのことを、最近なにかと話題のAIでなくとも、必要以上にスペックの向上したPCや電子機器、それらが机の周りにいやがおうに増えたコロナ禍をつうじて肌身で感じ取ったはずである。
そうして最近の科学技術が引き起こした事態を、さしあたり「グローバリゼーション」と呼ぶこともできそうである。ただし、その結果として文化の「均質化」や「分断」が生じていることもまた事実であろう。とするなら、半導体という科学技術が一国を代表するほどの影響力を持ちうるという事実は、ひるがえって国や文化として括られてきた従来の境界線、つまりはナショナル・アイデンティティが流動化していることを象徴しているのかもしれない。そもそも佐倉さんも指摘していたように、文化という対象が「一筋縄でいかない」のは、それがどれだけ均質に見えようとも「時間軸と地域差が絡み合った」網の目のような多元性を、本来的かつ潜在的に備えているからであり、このことはなにも台湾に限った話ではない。そして、そうであるはずの文化を同質なものとして見せかけるかのごとく、国家や国民という概念のもとに同じ言語を強制したり民族によって線引きをしたり、またはそれを科学技術やデザインで象徴させようと試みて(失敗して)きたのが、「近代」と呼ばれる時代であったはずだ。
なにもテクノロジーの進展が最近になって、従来の国民国家という枠組みをすり抜けたり破壊してくれるなどと楽観的なことを言いたいわけではなく、現実はそう単純ではありえない。実際、現在に頻発する戦争はそのことへの反動にも思えるし、そもそも半導体産業も大国間の駆け引きにおける重要なカードになっているという。より身近なところでも、いまだ科学技術による「立国」が喧伝されたり、それが「国民性」や気質と道徳的な仕方で関連付けられたりすることも少なくない。
しかしながら、西洋近代が先導してきた科学技術が今後、単一のものではなく、いかなる多様性を備えうるのかという問いに対して(佐倉さんはこれを「技術多様性」と呼ぶユク・ホイの議論をもとに指摘した)、半導体という着眼点は、それがもはや国家や理念ではなく、物質レベルから再考することが必要かつ不可欠であることを示しているように思われる。たとえば、科学技術に不可避についてまわる資源や廃棄物は実際に国家を超えでた循環を引き起こしており、そのことがひいては、自然‐文化という境界線をより根底レベルから再考しようとする最近の人類学や技術論を惹起してもいる。少なくとも、ここまでに「科学技術」と述べた箇所を「デザイン」に置き換えることはそう難しくないはずである。
(増田展大)
*なお、佐倉さんを今回のセミナーに迎え入れることができたのは、英国でデザインを学びながら、本センターのウェブサイトを見て連絡をくれた鈴木友里恵さんのおかげでもありました。記して感謝します。