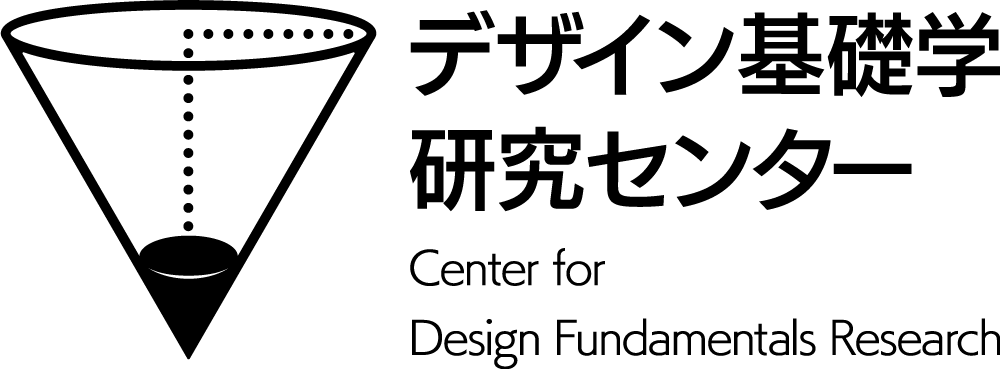コ・デザイン
Co-Design
近代化が進む中で「作り手」と「使い手」は徐々に切り分けられ、人々には「消費者」という呼称が与えられた。さまざまな領域において専門分化と領域の壁が生まれ、デザインも専門的な訓練を受けた人によって行われるものという捉え方が定着した。その一方で、本来存在している社会のさまざまな連関は見えにくくなり、特定の専門家の視座では手に負えない複雑な問題、厄介な問題が数多く浮上するようになっている。
こうした現状を受けて、一部のデザイナーや専門家などの限られた人々だけでデザインするのではなく、実際の利用者や利害関係者たちと共にプロジェクトをつくり、積極的に関わり合いながらデザインを進める取り組みが行われている。こうした取り組みは、閉じられた環境ではなく、積極的に開いていくことを志向するコ・デザイン〈Co-Design〉と呼ばれる。Coは、接頭語で「共に」や「協働して行う」という意味である。コ・デザインは、グラフィックやファッションなどのように成果物の領域を示すものではなく、デザインにおけるアプローチ(問題対象に接近していくための一連の取り組み過程や考え方)の一つである。
例として、「働きやすいワークプレイス」について考えてみよう。まず、人々は仕事場という環境の中で日々仕事を行う。他者と学びあい、自らの仕事を工夫し改変しつつ、日々の行為を営んでいる。そのデザインは、単純に什器や照明と言った空間のハード面だけで構成されるわけではなく、ベテランから新人まで多様な人々が知識を寄せ合い協力しあう仕事の体制、そうしたソフト面も含めて検討されなければならない。さらに今日では、感染症も考慮すべき事項である。多くの仕事場には急ごしらえの間仕切りが設けられ、そこはさらにオンラインと実空間が融合する場となった。
このように考えていくと、デザインの際に考慮すべき問題は、外部の〈系〉からは一方的に決められない要素で埋め尽くされていることが見えてくる。「ワークプレイス」とは単なる空間ではなく、生きた場であり、常に現在進行形である。ある特定の時間を切り取っただけで結論づけられるものではないし、その時に探り当てた答えが未来にもマッチするわけでもない。解は常に変動していく。その最終的に働きやすさを評価するのは、実際にその中で仕事に従事する人々の主観ということになる。したがって、これらをデザインするということは、代理人のデザイナーが魔法のように解決してくれるようなことではなく、働く人々、そこに来る客人、そして経営者など、そこに利害関係のある人々のそれぞれの現実を調停することであり、その決め事を巡る政治的な問題でもあるのだ。
こうした複雑さを伴ったデザイン――例えば、長期間関わり、使い手が学びながら変化していくもの、さまざまな利害関係者が存在するもの、事前の予測が成り立ちにくいもの――は、従来のようにクライエントの代理人としてのデザイナーがもつデザイン能力だけで対応するのは難しい。それゆえ、「ともに」取り組むアプローチが求められている。他者と協力しあってデザインに取り組むことによって、1)見落としがちな視点を提示する力、2)領域の壁やしがらみを破壊する力、3)当事者自身を力づけ持続させる力などを積極的に生み出し、個人でできる活動を超えることができる(上平、2020)。
このような、よりよい結果を導くための視点に加えて、もう一つ別の視点も挙げられるだろう。ともにデザインすることは、コモンズ(共有財)に関与する機会を生み出す。デザインは「みんな」で共有すべき問題であり、そのための一種の政治的側面も持つからこそ、一般的な正解ではなく民主的な「納得」のプロセスが重要である。しかし、しばしば専門家は人に指示できる強い立場に立ち、弱い立場にある者(当事者)の利益のためだと称して、本人の意思を問うことなく介入や干渉をしてしまう〈パターナリズム〉と呼ばれる問題を引き起こす。この問題は、医療において医者と患者の関係性として言及されることが多いが、デザインにおいても同様である。内部の人々が自己決定する権限をもたないことは、結果的に「おまかせ」や「あきらめ」の感覚を生むことになる。たとえ見えやすい結果につながらないとしても、問題に立ち向かっていくプロセスを共有しようと努めることは、関わる人々の距離を縮め、当事者意識を育んでいく。
コ・デザインは、1970年代の北欧の「参加型デザイン」と呼ばれる取り組みから発展するかたちで現在に至っている。参加型デザインのルーツとされるのは、計算機科学者・政治家のKristen Nygaardらが主導したノルウェーの鉄メタル労働組合における実践である(Nygaard and Bergo 1975)。彼らはSTS(科学技術社会論)の影響を受けながら、労働争議を調停する役割としてデザインを取り入れる試みを行った。経営者と労働者の距離を縮め、双方のパートナーシップを形成するために、積極的に現場に介入した。そして対話を起こし、参加を促す仕掛けとしてツールやゲームを開発した。これらは当初スカンジナビアン・アプローチと呼ばれ、のちに参加型デザイン(participatory design)と呼ばれるようになる(Gregory 2003)。参加型デザインは、対等な目線とそれぞれを尊重する姿勢を求めるためのものであり、民主的な社会を実現するためのコンセプトでもあった。
北欧の片隅で提唱された参加型デザインは、その後のデザインプロセスの理論にも極めて大きな影響を与える。人間中心デザインの国際規格(ISO 9241-210:2019)の源流となったほか、南半球の経済発展の中で民主化運動と繋がってアフリカやオーストラリア、南米などで広く取り組まれるようになった。21世紀に入ってからは、トップダウンのデザインに対する〈参加型〉という対抗的な取り組みのフェーズを超えて、より平等で密度の高い関与を求める〈共同性〉、〈協働性〉が志向されるようになり、参加型デザインよりもコ・デザインという言葉が使われることが増えている。
コ・デザインのアプローチは、狭義のデザインだけでなく、かたちのないサービスや組織のデザイン、さらには社会のなかの様々な分野で応用できる。北欧では特に活発であり、世界的に有名なDokk1(デンマーク・オーフス市)やOodi(フィンランド・ヘルシンキ市)などの大型公共図書館/コミュニティセンターが適用事例として知られるが、小さな自治体の公共施設をつくる際でも、利用者となる地域の人々がデザインプロセスの一部に関わることはごく一般的である。日本でも少しづつ取り組みが増えている。2022年にオープンした滋賀県長浜市の公設民営型のデザインセンター「長浜カイコー」は、コ・デザインのアプローチを取り入れている事例である。
ここで、〈コ・デザイン〉を標榜していなくても、協働的なデザインにとりくんでいる例は豊富に存在することに留意しておきたい。特に伝統的な文化の中には、持続可能で良質な協働の仕組みが成立していることが多い。その意味では、コ・デザインは新しい概念というよりも、近代化によって分断された「作り手」と「使い手」の距離を再度近づけようとする先祖返り的な試みであるとも言える。厳密な定義や範囲を求めるよりも、共同体の人々が発揮する創造性や、目の前にある小さなリアリティを尊重しようとする〈ともに生きる〉態度として捉えることが重要である。
また、人々が協働するのは、実際は人間だけに限らない。もともと人間は多様な種と協力しあって生き延びてきた動物である。より視点を広げれば、日々の食べ物の消化すら微生物との力を借りて行われている。気候変動の時代、人間だけを特別視することなく惑星全体への視点を持ったより包括的なデザインが求められている。コ・デザインの考え方は、そうした実践を考える際にも小さな手がかりとなるだろう。
(上平崇仁)
参考文献
- 上平崇仁 (2020)『コ・デザイン デザインすることをみんなの手に』NTT出版
- Gregory, J. (2003) “Scandinavian Approaches to Participatory Design,” International Journal of Engineering Education 19(1), pp. 62-74.
- Nygaard, K..and Bergo, O. T. (1975) “The Trade Unions. New Users of Research”. Personnel Review, Vol. 4 No. 2, pp. 5-10.