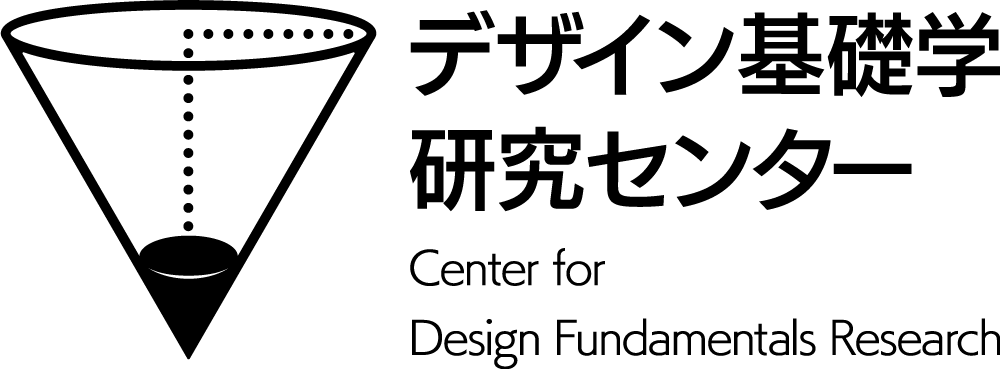第27回デザイン基礎学セミナー『路上のフェミニズム──キレイな都市を台無しにすること』
「ダイバーシティ」や「サステナビリティ」を掲げて進められる都市再開発の中で、貧困層やホームレスの人たちの追い出しが起きている。だが、路上の人々のうちには、身体性に基づく細やかな助け合いの関係が様々に張り巡らされている。都市の浄化に抵抗し自分たちの居場所を培う活動や、アートプロジェクトの事例について語る。
講師
いちむらみさこ(アーティスト)
プロフィール:東京の公園のブルーテント村に住み、物々交換カフェ・エノアールを開く。ホームレスのフェミニストグループ「ノラ」を発足。反ジェントリフィケーション、フェミニズムの展示・発表を国内外で行う。 フェミニスト雑誌『 エトセトラ』第7号「くぐりぬけて見つけた場所」(エトセトラブックス、2022)責任編集を務める。
日時
2023年5月26日 [金] 16:00~18:00(開場 15:50~)
会場
九州大学大橋キャンパス2号館 3階共用会議室+オンライン開催

レビュー
ひとがそこに「いる」ことの権利
いちむらみさこさんは、ひとがそこに存在すること、誰かの傍らにただ「いる」ことの尊厳について話をしたのだと思う。
アーティストのいちむらみさこさんは、東京藝術大学を卒業した後、既存のアートシーンではなく、公園で野宿をする人たちのところで自分の芸術やデザインの能力を活かしたいと考え、すでに 20 年ほどにわたって、そこで住居をともにしながら、そこを拠点に様々な活動を繰り広げてきた。
なぜいちむらさんは美術館ではなく公園を選んだのだろう。考えるに、公園の野宿生活においてこそ、人が生き存在するということが剥き出しになり、その根底的な次元に関わることでアートやデザインの核心が具体化できると、いちむらさんが考えたからであると思う。
路上や公園では、ひとびとは身近なもの、捨てられているものを様々に組み合わせることで自らの生存を保っている。その組み合わせのうちには、人の能力の組み合わせ、つまり人と人との助け合いもまた含まれている。公園には、散髪屋さん、大工さんなど様々な職能を持った人たちが住み込み、その人たちが自分の能力を活かし、互いに助け合って暮らしているといちむらさんは言う。だがそこにはむろん、職能ではない能力、ひとを気遣いケアする微細で繊細な能力も含まれている。
これらの組み合わせと助け合いのありさまこそが、いちむらさんの表現の基礎となる。野にある草花でも何か持ってくれば誰でもお茶が飲めるエノアール・カフェ(絵のあるカフェ)、野宿する女性たちの集まりである「ノラ」が開催するパンティー・パーティー(パン&ティー・パーティー)、女性たちのためのマトリューシカ布ナプキン、野宿者やそのほかの人たちに向けた Zine の発行など、誰かを支えることがそのまま表現となる多彩なアートをいちむらさんは繰り広げている。
野宿生活には夏の灼熱、冬の凍えといった自然の厳しさに加えて、通行人からのたえざる襲撃や嫌がらせがある。段ボールハウスが放火されるという衝撃的な事件に対して、いちむらさんは野宿者の段ボールをロケットに見立て、そのまわりに星をちりばめる「作品」を考案した。「ロケット」や「流星」と題されるこれら一連の作品群は、暴力行使を通行人に思いとどまらせる同時に、寝たままに都会の夜を旅するいしむらさん独特のファンタジーを表現するものとなっている。
他方で公園の野宿生活にはデザインの原初的なありかたが示されていると私は考える。生存限界に対抗する物資と能力の組み合わせ、互いの助け合いの工夫(devising)こそがそれである。脆弱であるとともに強靭でもある、そのような営みの積み重ねこそが野宿生活者の、野宿生活者としての尊厳をかたちづくる。そこにおいてデザインは明確で確固としたな意味を保つだろう。
とはいえ、そのような営みには次のような疑問を投げかける人もいるだろう。野宿者は公共の場を占拠している、「キレイ」な街を汚している、収容を拒否して好き勝手やっている、姿や匂いが不安で不快だ、結局のところどういう状態を望んでいるのかわからない、どこか見えないところに追いやって欲しい、と。
だが、私の考えでは、野宿の人々はこの社会が回転するときに必然的にいわば「分泌」されてくるものである。それだけにその人々の姿はこの社会の本当の姿を可視化していると思われる。だからこそ、この社会に適応して生きている人たちは、野宿の人たちを見て不安になる。きれいな自分は実は汚いのではないかと。
それは私もそうである。私がふだんの生活のうちで恐れ、否定しているものが、自分の生活の本当の姿として眼前に突き付けられる。だからそれを排除し、思わずそれに暴力を「振るってしまう」。自己自身を否定するこの強迫衝動こそが、世にいう差別というものの本質なのである。だからこそ、野宿する人に対する殺人や放火などの暴力を見聞きして、まるで自分がそれを行使してしまったかのように私は動揺する。自分はそんなことをするはずがないのに、それを日々なしているのではないかと。
「キレイな都市」を実現しようとするデザイン主体もまた、「役に立たない」、「たんなる」、「気持ち悪い」何かを自分のなかに抱え込んでいるのだと私は考える。そのような否定的なものを抑圧し、排除して、自分を「キレイ」に仕立て上げたとしても、そのようなデザインはその当人自身と決して和解しないし、これまでの強迫的な自己をただひたすらに強化するだけであろう。
既存の社会が分泌し、忘れ去っている野宿者という「存在」は、沈黙したその姿において、従来の強迫的な社会に反省を迫っているのだと私は考える。潜在的なその可能性を現実化することが、いちむらさんの「作品」が発揮するもう一つの力なのだと私は思う。自己自身の強迫性を解除し、自己の存在と和解して、自己変革することがその作品の希望である。
いちむらさんの「作品」が示しているのは、たんに生きていること、ただそこに存在していることの意味である。いちむらさんのアート活動において、これまで劣ったジェンダーだと誤って見なされ、社会に置き去りにされてきた女性的なるものと「路上」が接触するのも、おそらくはこの点においてであろう。それらの「作品」との向きあい方次第で、社会はその「存在」に助けられ、支えられることになると私は考える。
だとすれば、いちむらさんがいう「キレイな都市を台無しにすること」とは、役に立たないものと役に立つもの、存在するものと機能するものとの支えあいの次元を切り開き、まだ見ぬ都市の姿を妄想させる積極的なデザインを意味することになる。
(古賀徹)