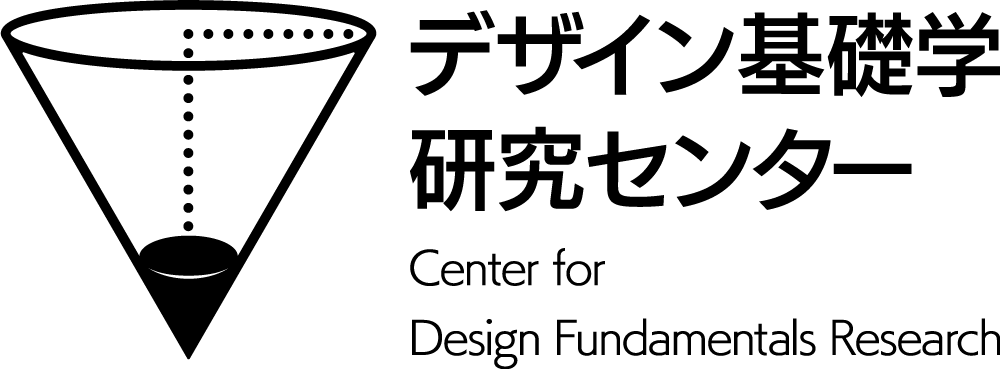第26回デザイン基礎学セミナー『存在論的デザインとは何か──デザインするのは誰?それとも何?』
デザインの達成目標としてウェル・ビーイングが言われて久しい。たんなる機能や利便性ではなく、存在そのものの〈よさ〉に焦点があてられるのはなぜだろう。近年注目されている「存在論的デザイン」の動向についてその基本的な考え方を紹介し、その可能性を探る。
講師
古賀徹 「存在論的デザインの基本的な考え方」
増田展大 「デザインの人類学的思考と存在論について」
日時
2022 年12月20日 [火] 17:00-19:00 (16:50開場)
会場
オンライン
*今回は外部講師をお招きする代わりに、デザイン基礎学研究センターのスタッフが内容をできるだけわかりやすくお話しし、皆様の質問に答えます。
お問い合せ
古賀徹(九州大学芸術工学研究院)
designfundamentalseminar@gmail.com
【主催】 九州大学大学院芸術工学研究院 デザイン基礎学研究センター
【共催】 九州大学芸術工学部芸術工学科未来構想デザインコース

レビュー
「存在論」という言葉を聞くと、その難解なイメージからどこか身構えてしまうところがある。だが最近になって、「存在論的」と称されるデザインの理論的動向が耳目に触れることも少なくない。製品や作品に限らず、生活環境やコミュニティの問題解決を目指すとされるデザインがなぜ、または、いかにして「存在論」と組み合わされることになったのだろうか。
第26回デザイン基礎学セミナーは、「存在論的デザインとは何か──デザインするのは誰? それとも何?」と題し、デザイン基礎学研究センターのメンバーがそれぞれに関連する議論を紹介した。まず、哲学を専門とする古賀が、その発信源の一つとしてアン゠マリー・ウィリスの論文を取り上げ、続いて後半部分では増田が、人類学者のアルトゥーロ・エスコバルによる著書『多元世界のためのデザイン(Designs for the Pluriverse)』から該当する章を紹介し、それぞれに考察を加えることで会場へと議論が開かれた。
前者のウィリスの議論の背景にあるのは、古賀によれば、近代のデザインを支配していた科学主義や実証主義への批判から、あらためて自然に接近しようとする志向である。「移行゠トランジション・デザイン」とも呼ばれるそれは、人間による一方的な技術開発が環境危機を招いたことへの批判と反省をもとに、従来の西欧/人間/男性中心主義を批判的に乗り越えようとする試みでもある。これと並行して、最近のデザインの目的のひとつには「ウェル・ビーイング」という言葉が頻繁に掲げられるようにもなっている。「より良い存在のあり方」を問うことは、そもそも「存在」とはいかなるものであり、それを「よくする」とはどういうことかといった問いを不可避に引き起こすはずだ、と古賀は指摘する。
こうしてみると、ウィリスの議論がハイデガーの議論に依拠して進められるのも不思議なことではない。人間が普段は意識しておらずとも「死に向かう存在」であることを自覚することにより意識化される存在そのものを討究したのが、ハイデガーの哲学であったからだ。こうした存在のあり方を道具(コップやハンマー)との関係において指摘した有名な議論を参照しつつ、ウィリスは人間と製作物゠デザインとの関係へとそれを展開していく。人間は一方的に人工物をデザインするだけでなく、特定の環境に埋め込まれた製作物によって自らの存在を意識させられるという意味において、製作物にデザイン「されて」もいるのではないか──これがウィリスによる議論の根幹を成す主張であり、存在論的デザインの中心的なテーゼとなる。
近代以降のデザインが、特定の意図や意思のもとに合理化や効率化を推し進めることで(人間以外の)対象を支配しようとしてきたのであれば、それはひるがえって、人間が製作した事物にデザインされる存在でもあることを忘却する過程でもあったと言えよう(近代の科学技術が推し進める前者を「メカネー(mechane))」と呼ぶなら、後者のように生きることと一体化した技術一般を「テクネー(techne)」として区別することもできる)。かくして現在までに西洋/男性/理性中心主義が支配的になったのも、そうした製作物からのフィードバックを抑圧したがゆえのことである。そのうえで古賀は、人間による一方的な自然支配という意図や意思からデザインを解放し、ときに人間以外の世界からデザインされることを意識化することを「存在論的好循環」と呼ぶと、その具体例として、国内各所で製作者や管理者が不明のままに利用されて残存する「勝手橋」や、または死を意識することをきっかけにそれまでのお役所仕事から脱する主人公を描いた黒澤明の映画『生きる』(1952年公開)を挙げて確認した。
ハイデガーへの理論的な参照こそ希薄にはなるが、増田の紹介したエスコバルの議論もまた、強烈とさえ言える近代批判が原動力となっている。エスコバルは先のウィリス(や、同じくデザイン理論家のトニー・フライ)の議論を参照しつつ、存在論的デザインの源流を1980年代以降の人工知能論(ウィノグラードとフローレス)やオートポイエーシスの概念(ヴァレラとマトゥラーナ)に遡ってみせる。これらの議論が存在論的デザインの源流とみなしうるのは、デザインを実践する主体と自然や文化といった対象との分割を当然視してきた近代主義(または、デカルト主義)からの脱却を、早くから試みるものであったがためである。
エスコバルが挙げるように、最近のスマートフォンを事例に考えてみても良い。その利便性や効率化が謳われる一方で、実際のところ、スマホを駆使する私たちはしばしば偏った意見へと分断され(文化)、そのために必要となる技術開発がグローバルな格差問題を引き起こし(技術)、過度のエネルギー消費と資源開発(自然)にまで結びついている(そして、そのことを私たちは見て見ぬふりをしようとする)。とはいってもテクノロジーを手放し、前近代的な体制へと後戻りすることが不可能であるなか、文化や技術や自然といった対象と人間主体との対立を前提とした近代モデルを、デザインはいかにして乗り越えることができるのか。このような問いに対し、エスコバルもまた存在論的デザインの考えを召喚すると、彼が言うところの「多元世界」への移行を訴える。科学技術による発展を目指す近代社会がその実、現在までに西欧/男性中心主義的な「単一の世界しかない世界」に陥ったのに対し、それと対置される多元世界とは、それぞれに人間と非人間から成立する自己創発゠自治的な複数のコミュニティから構成されるものとして位置付けられる。そして、そのうちで重視されるのも、良く生きることを意味する“Vivir Bien”にほかならない。
こうしてエスコバルもまた、多元世界への移行のために「デザインされる存在」としての人間やコミュニティの関係性を重視するのだが、肝要なのはその関係性に人間やその制作物だけでなく人間ならざるもの、具体的にはテクノロジーや動植物までもが含まれていることである。この点は人類学とも関連の強い分野として、人間以外の行為主体性を重視するアクター・ネットワーク理論(ブリュノ・ラトゥール)や、人間存在を他種とのからみあいから再考するマルチスピーシーズ民俗誌(アナ・チン)など、最近の動向とも連動したものであるのだろう。このことを確認したうえで増田は、多元世界への移行の一例をデンマークのごみ処理場が辿った固有の歴史を事例に、人間とテクノロジー、動植物や微生物が織りなす複合的な関係を指摘した論考「荒廃地のエコロジー」のうちに確認した。
以上のように、存在論的デザインを主導するふたりの理論家を導き手とした今回のセミナーには、大学関係者以外にも企業や行政の分野から多様な参加者が集い、その後の議論も活発なものとなった。例えば、人間以外の動植物をデザインの行為主体とみなす場合に問い直される「デザイナー」の存在や役割について、またはハイデガーと関連する他の哲学の系譜(西田幾多郎の主客合一やオブジェクト指向存在論など)とデザインの接合の可能性といった論点である。その詳細を紹介することは叶わないが、これらの議論によって存在論の難解さが少しでも噛み砕かれ具体化されると同時に、デザインについての批判的思考が深化されるのであれば、それもまたひとつの「好循環」であったと言えるかもしれない。
なお今回の企画は、前回のデザイン基礎学セミナーにご登壇頂いた上平崇仁氏の議論を受けて発案されたものであり、今回の研究会の内容についても後にレビューを頂いたことを記して感謝したい。